今や全国的にみても中学受験をする子どもは右肩上がりの傾向だそうです。子どもが小学校に上がってしばらくすると「中学受験をするのかしないのか」について悩む方もいらっしゃると思います。
我が家の子どもが塾通いしてから1年が過ぎましたが、選ぶときにこんなことをもっとよく考えていれば良かったと思うことを実体験から9つにまとめてみたので参考にしてください。
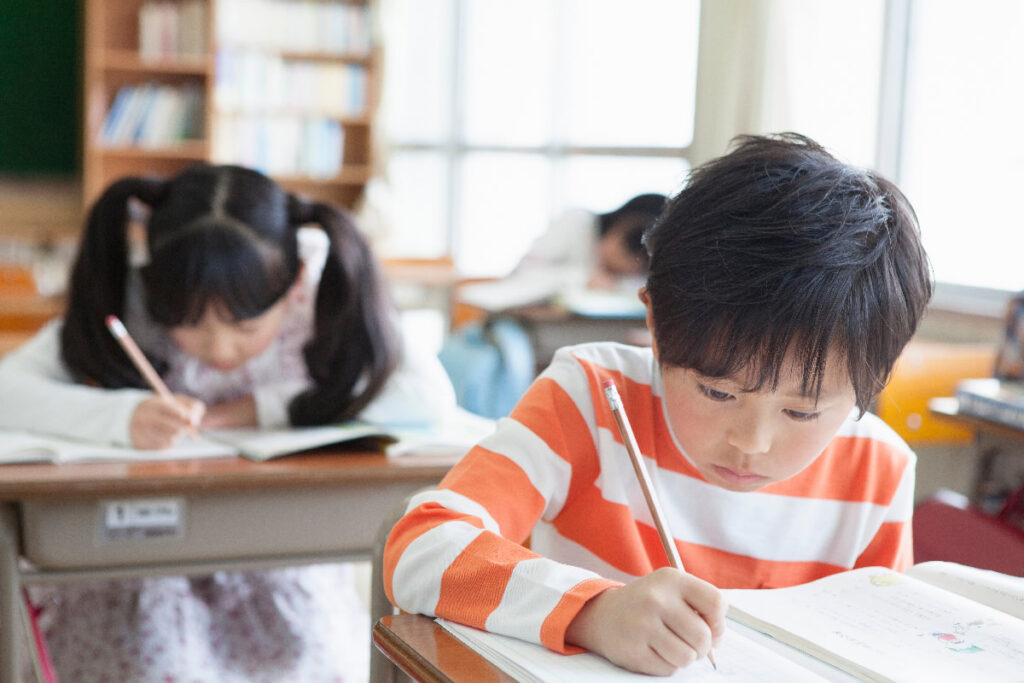
中学受験の塾選びの9つのポイント!
それでは実際入塾する際の塾選びについてのポイントを順を追って解説します!
塾選びの9つのポイント① 入塾に向けての下調べ
私も夫も中学受験を経験したことがなく、子どもにも中学受験は全く考えてませんでした。
そんな私が子どもに中学受験をさせてみようと思ったきっかけは子どもから「中学受験をしたいから塾に通いたい」と言い出したからです。
子どもは学校のお友達が次々と塾通いするのを目の当たりに見て子どもの気持ちは揺るがないものになっていたようです。
私はそんな子どもを横目で見ながら半年くらいの間はやり過ごしていたのですが、何度も何度もあきらめることなく「受験がしたい!塾に行きたい!」と言うので、中学受験を見据えて塾に行かせることにしました。周りと10ヵ月近く遅いスタートでした。
大概の方が無意識にやっていることだとは思いますが、私自身はこの下調べを飛ばしていたので改めて書き出しました。入塾を検討する前にやっておいたほうがいいこと3つです。
- 自宅の周りにどれだけ塾があるのかを調べる
- ご近所やママ友の評判・子どもの学校の友達からの情報を集める
- ネットで塾の情報を調べる
自宅の周りにどれだけ塾があるのかを調べる
私は塾を選ぶ時に下調べをあまりせず勢いで決めてしまったのですが、ある程度どんな塾があるのかを事前に調べておくと比較する際にスムーズだったなと思いました。近隣の塾の評判などもリサーチしておくといいと思います。
ご近所やママ友の評判・子どもの学校の友達からの情報
私自身ママ友の交流があまりないため情報を得る機会はありませんでしたが、相談できる方はぜひ取り入れた方がいいと思います。子どもが学校から聞いてくる情報も決して鵜呑みにはできませんが、周りの子ども達の今現在の状況を知る手がかりにはなると思います。
ネットで塾の情報を調べる
今日本にはどんな塾があってランキングや評判はいかほどなのか、授業の進みぐらいやフォローの体制など塾によって特徴がありますので、調べるに尽きると思います。
ある程度情報や評判を集めた上で塾の見学(体験)・説明を聞きに行くと判断もスムーズにできると思います!
受験指導専門家( 西村先生)のYouTube動画は塾選びだけでなく、親としての心構えなどで参考になりました。
以下の動画は個人的に中学受験を考えた時に見たかったな!と思う動画です。
塾選びの9つのポイント② 「集団か個別か」「大手か個人か」
集団か個別か
一人一人とじっくり向き合ってくれるところがいいのか、集団でワイワイ勉強した方がパフォーマンスが上がる子どももいるので、その子に合ったところで家族の意向で決められるといいですね。
あくまでも個人的な見解ですが(他者とのレベル感や競争意識が芽生えない恐れがあるので)まずは個別塾よりも集団塾の方がいいのかなと思います。
個別塾の利用については様々だと思いますが、弱点分野の補強に利用されている方も多いようです。
大手か個人か
大手塾か個人塾かによってもぜんぜん感覚が違ってくると思います
大手塾は最新の受験に関する情報を常にアップデートしているところが魅力です。受験の傾向なども常に分析して生徒に提供しています。大手塾は頻繁にクラス変えがあったり先生が都度変わるため、その環境に馴染めずストレスになってくる子どもも少なからずいると聞きます。
うちは個人塾には通わせたことがないため参考にならないかもしれませんが、個人塾はクラスも先生も変わることがないためじっくり生徒一人一人に向き合ってくれるところが魅力です。
そして個人塾はいろいろと融通が利くのもメリットになるようです。反面、最新の情報については若干遅れがでるとも聞いたことがあるので、家庭の考え方や子どもの性格などを合わせて検討されるといいですね。
塾選びの9つのポイント③ 「志望校の大まかな設定」
最終的にはどの方向で受験させるのか?たとえば公立受験か私立受験かによっても通う塾は違ってくると思います。
よく聞くのが最初から適性検査型(公立)の勉強だけをしてしまうと、もう私立受験は無理だと聞きます。なぜなら私立受験の試験範囲は広範囲になるので、これらを勉強していないことには歯が立たないそうです。
後に転塾するにも、私立型の勉強から適性検査型の勉強に切り替えることは可能でも(6年生の夏以降でも)その逆はとても難しいようです。これから入塾を考える際にかなり重要になってくると思います。
塾選びの9つのポイント④ 「勉強の進むスピード」や「宿題のボリューム」を見比べてみる
塾によっては御三家などを意識した受験でハイスピードに授業が進んで行く塾もあれば、中堅校ねらいのじっくり授業を進める塾もあります。宿題についても大量に出る塾もあれば、基本的に出さない塾もあります。
また、同じ塾でも教室の塾長の方針によっては宿題にもかなり影響が出てくることも知っておいてほしいです。
大手塾などの先生は年に数回移動があります。私が「へえ~」と思ったことは、更に塾長にも移動があるのです!塾長一人変わっただけで塾内の雰囲気が一気に変わります。
我が子の場合、1度転塾を経験していますが、転塾前の塾の塾長が途中で変わりました。変わった瞬間、宿題のボリュームが一気に増え、提出期限まで変わったので親子で慌てた経験があります!塾長恐るべしです!
新しい塾でも、同じ系列の塾なのに隣駅の塾ではのんびりほんわかモードに対して、我が子が通っている教室はかなり気合が入っており塾内がピりっとした空気感で授業を行っています。まったく同じ塾でもこうも違うのかとかなり驚いた経験があります。
塾選びの9つのポイント⑤ 「自宅から通いやすい場所かどうか」
6年生ともなると一週間で塾に通う日数がどんどん増えます。お子さんが通いやすい場所でないと移動時間だけでも大変ですので、検討のポイントにしておいた方がいいでしょう。
また、お迎えは誰が行くのかどうするのかについても最初に取り決めをしておくといいですね。我が家の場合ですが週のほとんどを夫が仕事帰りに迎えに行ってくれているので、旦那さんの協力も不可欠だと痛感しています。
塾選びの9つのポイント⑥ 「授業終了時間」、「晩御飯の時間」
個人的にはとても重要だと思います。帰宅時間が遅くなると当然晩御飯どうするの?の問題は浮上してきます。
例えば日能研などの塾のように晩御飯を宅配で注文を受け付ける塾もあるようです。その他市進塾など19:00台の早い時間に授業を終わらせるような塾もあります。
子どもの性格によっては塾弁食べづらいと言って塾弁を食べきれないお子さんもいると思うので(実はうちの子がそうです。)見学の際のチェックポイントとしてもいいと思います。

塾弁は教室によって実施しているのかどうか事前に確認してね
また、ありがちなのが授業が長引いて終了時間が大幅に遅れてしまうことです。
大概の塾は入退室の際にカードをかざすことによって保護者にメールで入退室の通知が届くようにしていますが、子どもによってはカードをかざすことを忘れてしまう子もいます(うちの子は未だに頻繁です)。
我が家はキッズ携帯を持たせて終わった際には必ず連絡をするようにさせています。
携帯を渡すなどの対策をとっていても、入学したり進級してすぐの頃は勝手がわからないため、無駄に待つことも多々ありました。結構待っている保護者の方も多かったりで何か改善方法がわかればいいなと切に思います。
塾選びの9つのポイント⑦ 「塾の見学」もしくは「体験」をする
これはもう入ってみないとわからない部分もあるのですが、子どもがその塾に合っているのかどうなのか、先生と合いそうなのかどうなのかは、子ども自身が見学や体験をすることでわりと瞬間に分かったりするようです。
我が家の場合は少人数制の塾と大人数の塾と最初見学に行きましたが、特色が全然違うため比較できてよかったと思います。子どもも体験を通してその日のうちに「ここがいい!」と言ってきたので体験は必要だなと思いました。
雰囲気も教室によって本当に千差万別で、活気がある教室や生徒自身が伸び伸び勉強しているかも参考にしたらいいと思います。
塾によってはだらけ切ったところもあれば、スパルタでピリピリしているところもあるので1校で決めてしまうのではなく、可能な限りいろんな塾を見学された方がいいと思います。
問い合わせに対してスピーディな対応をしてもらえるのか、先生方の授業やフォローに対する取り組み方も見学の際にチェックできたらいいですね。

同じ塾でも教室によって全く雰囲気が異なることもあったわ!
あと一つ付け加えておきたいことは、保護者と塾との連携の取りやすさです。
今わが子が通っている塾は子どもの自主性を重んじることをモットーとしている人気校ですが、少々スパルタな雰囲気でそこが気にいって転塾を決めたものの、転塾したばかりの頃など子どもも私もわからないことなどがあった時にとても問い合わせられるような雰囲気ではなく、今でも相談しづらさを感じます。
保護者と塾との関わり方がある程度親密であった方が子どもの受験に対しての不安感などある程度払拭できるのでこの辺りも押さえておいた方がいいと思いました。
塾選びの9つのポイント⑧ 「費用の概算」をする
塾通いは4年からスタート(3年生の2月より)するところがほとんどですが、年々塾代も上がっていきます。
私はうっかりすべての学年の塾代を網羅して見積もっていませんでした。4年なら4年のみの年間の概算しかみておらず、(5年の時は5年になってから考えればいいわ~)なんて呑気に思ってたので、年々上がっていく塾代に愕然としました。6年になると本当に爆上がりします!
塾代ですが、ざっとですが月々の塾代以外にも結構出費があります!
- 季節講習(春期、夏期、冬期)
- ゴールデンウィーク、日曜特訓、試験前の特訓などスポット的な講習(任意)
- 合宿(任意)
- 模試、合否判定などのテスト代
- シーズンごとのテキスト代
月々の塾代に実際これだけ加算されると結構家計を圧迫します!塾によって金額も様々なのでよくよく吟味してから決断しないといけなかったなと反省しています。
最初に説明を受ける際に資料をもらえると思うのですが、費用面は隅々まで目を通しておいた方がいいです。
塾選びの9つのポイント⑨ 学校のお友達と一緒になる可能性について
学校のお友達も一緒に通った方が子どものモチベーションも上がり意欲が増す子もいれば、一緒に通うことでだらけてしまって勉強に身が入らない子もいると思います。
子どもの性格によっては学校のクラスメイトのだれもいない方が伸び伸びと勉強に打ち込めるからと、家からわざわざ遠いところへの入塾を決めた方の話も聞いたことがあります。
帰りもお友達と仲良く帰れる方がいいのか、トラブルは避けたいから誰もいない方がいいのか(お迎えに関してはママ同士のお迎えのトラブルも少なからずあるようです)結構大事だと思います。
ちなみにうちの子は最初に通っていた塾では、学校のクラスメイトの子が何人もいたことで塾に対してすんなり入り込めたことや、モチベーションが上がったことはプラスにはなりました。
しかし、近所の子と塾が終わってから自転車で帰宅する際おしゃべりに夢中になって帰宅が遅くなることもあり、毎回心配しながら待っていることも多々ありました。
入塾の際にはあまり考えてなかったポイントだったので特記しておきたいポイントです。
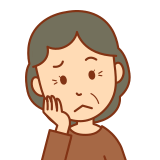
なかなか軽視できないのね
まとめ
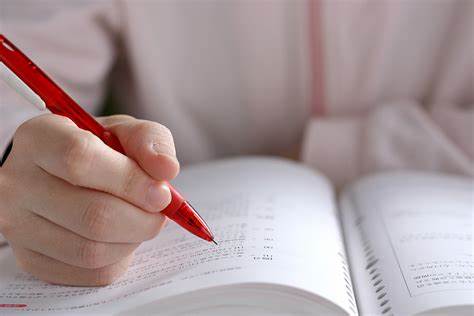
いかがでしたか?
塾選びの際の9つのポイントをあげていきましたが、これら8つ全てを満たせる塾を探すのはハードルがかなり上がってしまいます。
子ども本人にとって何が一番大事に思っているのか、大事にしてあげたいのか、また家庭によっても自身でも譲れないポイントが出てくると思うので、そこを重視して決められたらいいと思います。
今まさに中学受験をさせようか塾を検討しようかどうしようかと検討されているママ・パパのなんらかの参考になれば幸いです。
中学受験は親の受験とはよく言ったもので、塾に入って受験勉強がスタートすると私の場合は本当に翻弄されます。
一番大変なのはもちろん子ども自身ですが、なにせ小学生なので全部子ども任せにはできず、いろいろとサポートすることもあるんだなあと痛感しています。この辺りのことも追々ブログにできたらいいなと思っています。
それではまた!
(併せて読みたい)


