寒ーい冬には欠かせない方も多い湯たんぽ。一口に湯たんぽといっても様々な種類がありますし、用途もいろいろです。そんな湯たんぽについてまとめてみました。
湯たんぽを使いだしたきっかけ
私は元々極度の冷え性で、寒い日の夜など足先が冷えてなかなか寝付けないことが多かったのがきっかけです。
実はあまりにも足が冷えて寝付けないため、間に合わせでペットボトルの空にお湯を入れて2~3日使用していました。
さすがにむき出しの使用は危険なので水を入れて温度を下げたり、タオルを巻いたりしてしのぎました。
この経験から、(これは災害時に使える!)と確信しました。本当に急場の場合は空のペットボトルおススメです!

もし使用するならペットボトルの材質は固いものをえらんでね!
世の中いろいろな暖房器具がありますが、私が湯たんぽを使い続ける理由は、静電気が起きにくいと聞いたことがあるからです。
一説によれば、静電気が溜まると疲れやすくなったり疲労感がぬけなかったりの弊害があるとのことなので(聞いた話ですので確証はありません)静電気をなるべく身体に溜めない方がいいようです。
自然のお湯のみで身体に優しいと感じることや、お湯を入れるだけでほったらかしにできちゃうことと、故障の心配もあまりないのでずぼらな私にはぴったりだなと思い湯たんぽを使用しています。
ちなみに私が使っているゆたんぽはファシーの湯たんぽです。身体にフィットするのと、カバーのデザインが可愛いのが多いので使用しています。

自宅で使用している湯たんぽと同じ種類のものです。
こちらは日中お腹が冷えて痛くなったり(極度の冷え性のため)生理痛などでしんどい時にお腹や腰を温めるために使用しています。
夜寝るときの足用の湯たんぽは同じファシーのものでフラットなカバーのものです。
湯たんぽを使ってからは本当に眠りが快適になりました!今では冬場は子どもも一緒にそれぞれのMY湯たんぽを使用して眠りについています。
湯たんぽの始まりは?
記憶にある幼少期からすでに私達の周りにあった湯たんぽですが、古くは中国から発祥した湯たんぽは、「湯婆子(タンポツ)」といい、「婆」は妻のことを指すので、布団に入れて足腰を温める“お湯の妻”の意味だそうです。
日本にはなんと室町時代に伝来し、「湯」を“タン”と読むことがわかりづらく、「たんぽ」に「湯」を重ねて「湯たんぽ」と呼んだのが日本での湯たんぽの始まりです。
江戸時代には徳川綱吉が使用したとされる犬型の湯たんぽも存在していたようです。湯たんぽにもお犬様!とても愛着を持って使ってたんでしょうね。
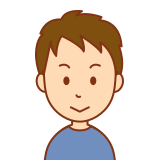
今も昔も冬は寒いからね
明治時代になると陶器製の湯たんぽが作られるようになり、大正時代にはトタンの湯たんぽ、戦後はプラスチック製やポリ塩化ビニル製のものが湯たんぽの主流となって現在に至るようです。
湯たんぽについて引用
湯たんぽ – Wikipedia
湯たんぽのメリット&デメリットは?
そんな湯たんぽのメリットデメリットはどんなことがあるのでしょうか?

メリット
冷え性改善
湯たんぽのいいところは、体に直接あてることができるため冷え性改善に効果的です。
また、生理痛などお腹や腰を温めると痛みが和らぎます。冬場だけではなく夏場エアコンの効いた部屋での使用もおススメです。
エコ・災害対策
湯たんぽはお湯さえあれば体を温められることと、布団に入れてしまえば朝まで使えるので節電にもつながります。
そして繰り返し使用できるため、ランニングコストもかからず経済的です。温度が下がっても洗濯などに再利用できるのもメリットと言えますよね。
また、湯たんぽは持ち運びやすいので、屋内屋外を問わずに使用できる点もメリットです。手軽に持ち運びができることから、災害時の防災グッズとして準備しておくと良いと思います。
避難生活での寒さ対策どうする?新聞紙・段ボール活用術!ペットボトルを湯たんぽ代わりに!
避難生活での寒さ対策どうする?新聞紙・段ボール活用術!ペットボトルを湯たんぽ代わりに! | NHK
故障・火災の心配がない
電気などを使用することない湯たんぽは、故障の心配がないことは大きなメリットです。
夜寝ている間に電気系統の故障による火災などの心配もないのは安心ですね。適切なメンテナンスを行えば長く使えることや、その他の暖房器具などと比べると安価で手に入るのも魅力です。

デメリット
やけどに注意
湯たんぽのデメリットといえばやけどです。
直接熱いお湯を扱うので注ぐ時も使う時も意識して扱う必要があります。普段扱っているうちにうっかり忘れてしまいがちな基本的な対処法が以下になります。
- 平らで安定した台の上に置く:不安定な場所でお湯を注ぐのは危険です。また、お湯が注ぎ口から溢れてしまっても早急に対処できます。
- じょうごを使う:湯たんぽの注ぎ口が小さい&やかんなどの注ぎ口が太い場合にも有効です。
- カバーをつける:カバーはやけど防止に役立ちます。カバーをつけることで熱すぎずちょうどいい温度で使用できます。
- 蓋をしっかり閉める:使用している時に蓋がゆるむ可能性もあるので、確認はしっかりして使用しましょう。
湯たんぽを使う上で「低温やけど」に注意が必要です。
低温やけどを防ぐには長時間同じ場所での使用を避けることが有効です。
ある程度身体が温まってきたら、身体から少し離した状態で眠りにつくのが安心して寝れますよ。
「低温やけど」ってどんなやけど?
冬場に注意 低温やけど | 済生会 (saiseikai.or.jp)
製品の注意事項を確認する
湯たんぽの製品ごとに耐熱温度が違うので、誤った使い方をすると破損や火傷の原因となります。よく確認した上で使用しましょう。
湯たんぽについての記事は以下のPart2へ続きます。



